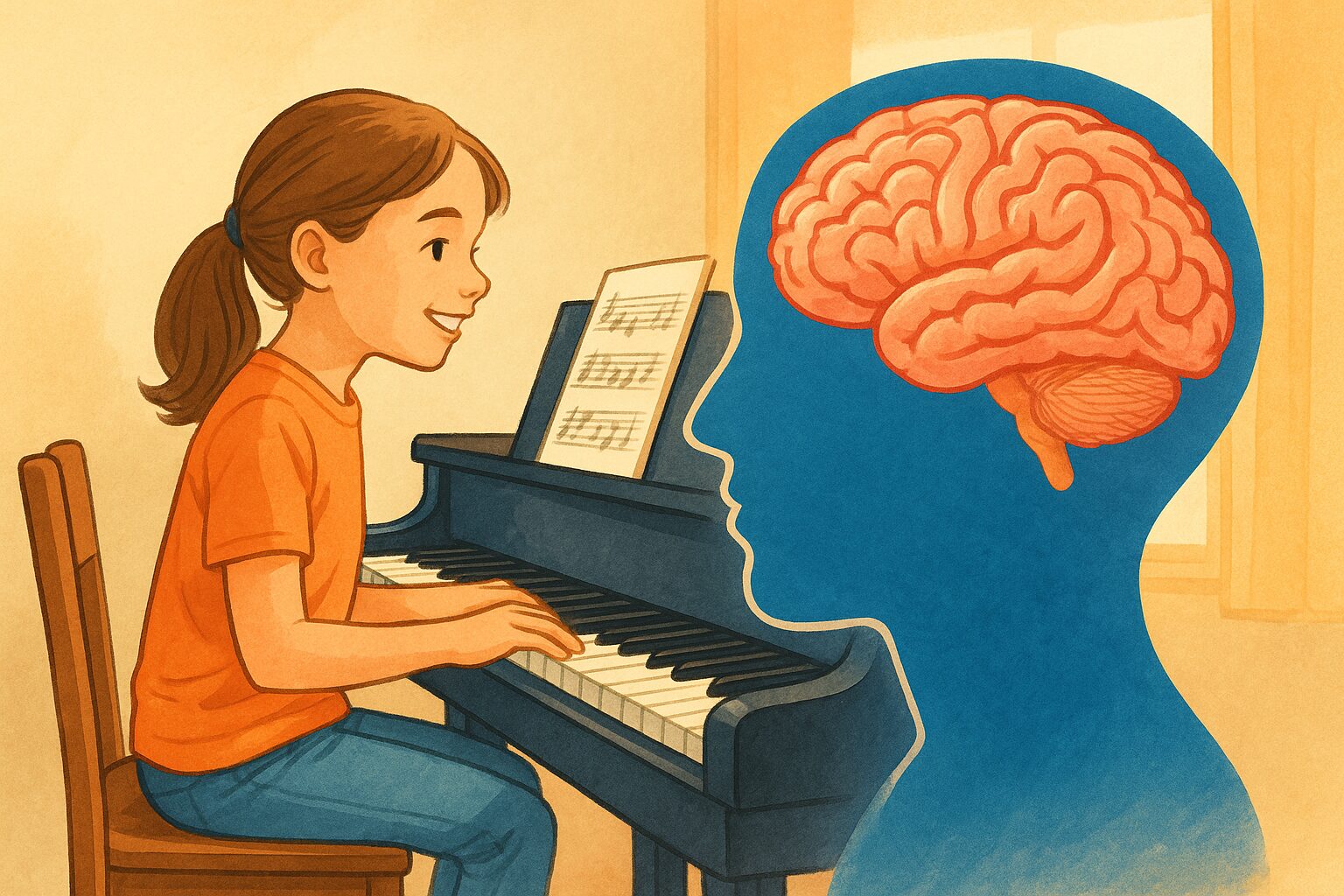~薬剤師ともが伝える、子育てに科学を取り入れる方法~
はじめに
こんにちは、薬剤師の「とも」です。
子育てをしていると、「習い事ってやっぱりさせたほうがいいの?」「何をどのくらいさせるべき?」と悩むこと、ありますよね。
わが子にとってベストな選択をしたい。でも情報があふれていて、何が本当に効果的なのか見極めるのは大変です。
そんなときにぼくが頼るのが科学的根拠=エビデンスです。
今回は、放課後の習い事が子どもの学力や性格(非認知能力)に与える影響を調べた、アメリカの大規模な研究(Durlak et al., 2010)をもとに、習い事が子どもにどう作用するのかをわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 放課後の習い事が子どもの学力にどんな影響を与えるか
- “非認知能力”って何?将来にどう関係する?
- 効果的な習い事の選び方とNGパターン
- 習い事を「科学的に成功させる」4つのポイント
放課後の「習い事」は本当に意味がある?
結論:意味あります!でも“中身”が大事。

Durlakたちが行ったのは、全米の放課後プログラム75件をまとめた大規模研究。
「習い事」や「放課後活動」が、どのくらい子どもの成長に影響を与えるかを統計的に分析したものです。
その結果…
- 学力の向上(成績やテストスコア)
- 社会的スキルの強化(協調性、自己主張)
- 問題行動の減少(いじめ、暴言、無気力)
…など、全ての面で効果ありという結果が出ました。
特に印象的なのは、「SAFE」と呼ばれるプログラム設計をしている活動では、さらに効果が高いということ。
“非認知能力”ってなに?なぜそこが大事なの?
習い事の効果は、単に「勉強ができるようになる」だけではありません。
今、教育界や心理学で注目されているのが非認知能力です。
非認知能力とは?
- やる気
- 自己肯定感
- 感情のコントロール
- 他人とうまく関わる力
- 粘り強さ・集中力
…など、テストでは測れないけれど人生に超重要な力です。
非認知能力が高いと…
- 学校生活がうまくいく
- 社会に出てからの人間関係もスムーズ
- 挫折しても立ち直れる
など、将来の“生きる力”の基礎になると考えられています。
Durlakの研究では、放課後活動に参加した子は非認知能力が高くなる傾向がはっきりと見られました。
どんな習い事がいいの?失敗しない選び方
習い事なら何でもOK!…ではありません。
効果が高いのは「SAFE」な習い事

SAFEとは以下の頭文字です。
| 要素 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| S:Sequenced(順序立てた) | スキルを段階的に教える | 教材がレベル別に分かれている英語教室 |
| A:Active(能動的な) | 子どもが体験しながら学ぶ | 実践型の理科実験、演奏、対人ゲームなど |
| F:Focused(集中できる) | 特定のスキルに焦点を当てる | 単に預かるだけでなく「そろばん集中指導」など |
| E:Explicit(明確な目標) | 教える目的や成果がはっきりしている | 「○級合格」「発表会参加」などゴールがある |
SAFE要素がしっかりしている習い事は、学力・非認知能力ともに効果が高いと明記されています。
習い事の“やりすぎ”がもたらす落とし穴
習い事がいいと聞くと、「たくさんやらせたほうがいいのかな?」と考えてしまいますよね。
でも、詰め込みすぎは逆効果になることも。
- 子どもが疲れて、かえってイライラ
- 親子で喧嘩が増える
- 「やらされ感」で学ぶ楽しさが消える
論文でも「質>量」と明言
Durlakらの研究でも、「ただ通っているだけの習い事」では効果が低く、
SAFE型で質が高い習い事を1〜2個、無理なく続ける方がはるかに効果的だと報告されています。
習い事を「科学的に成功させる」4つのポイント

薬剤師として「根拠ある子育て」を大切にしているぼくが、Durlak論文をふまえて提案する「習い事成功のコツ」をご紹介します。
- 子どもの“興味”を最優先
→ 親の希望より、本人が「楽しい!」と思えることが続ける力の源です。 - 週に2〜3回までに抑える
→ 余白のあるスケジュールが創造性や心の安定につながります。 - SAFE型の教室を選ぶ
→ カリキュラムが明確、子どもが能動的、目標があるのがチェックポイント。 - 定期的に振り返る・やめ時を決めておく
→ 「今の教室、合ってるかな?」を3ヶ月に1回くらいのペースで見直すのがおすすめです。
まとめ:放課後の過ごし方が人生をつくる
放課後の1時間、2時間はただの「空き時間」ではありません。
“学力”だけでなく“人間力”まで育てるゴールデンタイムなんです。
今回ご紹介した研究(Durlak et al., 2010)は、
「どんな子どもでも、質の高い習い事を適切に受ければ、確実に良い影響がある」と強く示してくれました。
最後に:科学で、子育てはもっとラクになる
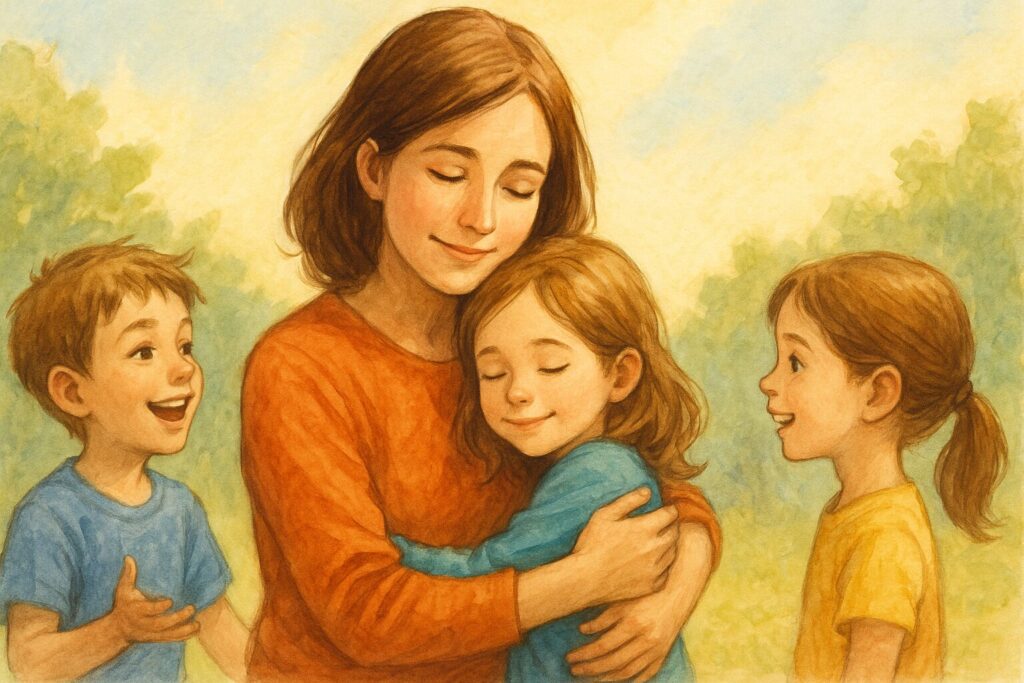
子育てに真剣な親御さんは、真剣ゆえに「これで本当にいいのかな?」と不安になってしまいがちです。
でも、科学の視点を持つことで、安心して子育ての選択ができるようになります。
これからも、「薬剤師とも」として、医学・心理学の研究をわかりやすく翻訳する子育てブログをお届けしていきます。
次回もお楽しみに!
参考文献
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., & Pachan, M. (2010).
“A meta-analysis of after-school programs that seek to promote personal and social skills in children and adolescents.”
American Journal of Community Psychology, 45(3-4), 294–309.
https://doi.org/10.1007/s10464-010-9300-6 - Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL).
The SAFE framework for effective SEL programming.
https://casel.org/
アドバイザーランキング